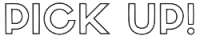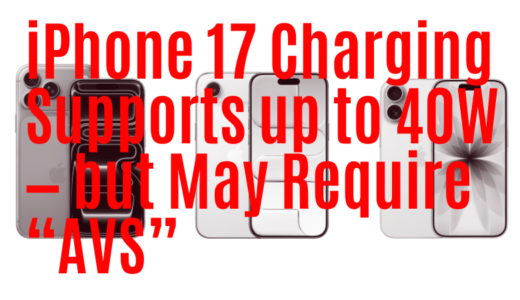このページのリンクには広告が含まれています。
「今年のiPhone、カメラは何が変わった?」――結論からいえば、ズームの“実用域”が伸び、動画の“制作域”が広がったのがiPhone 17 Proの本質です。
背面すべてが48MP化した三眼構成に、最長“200mm相当”まで到達する最大8倍の光学ズーム。
さらに動画はProRes RAW/Apple Log 2/ACES/Genlockと、既存のスマホの枠を越えるプロ仕様まで到達しました。
まずはハードと機能の全体像から見ていきます。

ガジェットブロガー
バビ
東京在住のガジェット好き会社員ブロガー。
デザイン性の高いガジェット・スマホ・PC周辺機器を、実体験にもとづき200本以上レビューしています。
経験を活かした専門的かつ正直なレビューをお届けします。
Lit.Link
INDEX close
- ハードの要点:iPhone 16 Proと何が変わったか
- 写真:何が新しく、どこまで撮れるようになった?
- “8×光学品質”の正しい理解:物理光学ズームではなく、高解像クロップで画質確保
- フロント18MP×センターフレーム:グループセルフィーと縦動画の快適さ
- 動画:ProRes RAW/Apple Log 2/ACES/4K120 Dolby Vision、そしてGenlock
- 実務ワークフロー:機動力と編集耐性のバランスをどう取るか
- 弱点と注意点:200mmの暗所・熱設計・容量
- 17 Proの“画づくり”の傾向:iPhoneらしさのまま“引き延ばせる”
- まとめ:今年“買い替える理由”は、ズームの「使える」進化と動画の「繋がる」進化
ハードの要点:iPhone 16 Proと何が変わったか

iPhone 17 Proのカメラは、「光学4×+“光学品質”8×」の二段ズーム構成に刷新され、さらに背面3カメラすべてが48MP化しました。
テレフォトは次世代テトラプリズム+56%大型化センサーを採用し、100mm(4×)は純粋な光学ズーム、200mm(8×)は48MPテレセンサーの中央12MPを使う“光学品質”モードという整理が公式表記に即した理解です。
なお、200mm(8×)は12MP出力の“光学品質”モードで、48MPテレセンサーの中央部を用いて解像感を確保します(100mm(4×)は純粋な光学)。
(同じように、2×(48mm)は12MP出力の“光学2倍相当”で、メイン48MPセンサーの中央部を使用します。)
ズームは、8倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、合計16倍の光学ズームレンジをカバーします。
加えて、0.5×/1×/2×/4×/8×の5段階を軸に、13/24/28/35/48/100/200mm(+マクロ)と“8本の仮想レンズ”を明示するUIで、撮影意図に合わせた焦点距離選択がより直感的になりました。
前世代のiPhone 16 Proは、メインと超広角が48MP、テレフォトは12MP・120mm(5×)でした。
これが17 Proではテレフォトも48MP化され、最長到達は「最大8×の光学品質ズーム(200mm相当)」へ。
光学品質ズームの“品質”は、レンズ可動ではなく高解像センサーの活用で画質を担保するという意味で、Appleの公式仕様文言も“optical-quality”と明言しています。
結果、8倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、16倍の光学ズームレンジとなり、被写体までの距離に応じた使い分けがしやすくなりました。
動画面でも17 Proは進化が大きく、4K/120fps Dolby Visionにくわえ、ProRes RAW・Apple Log 2・Genlockを世界で初めてスマートフォンでサポート(Final Cut Camera 2.0/Blackmagic Camera連携)。
マルチカム同期やLEDウォール撮影でのフリッカー回避など、プロ現場のワークフローへの親和性が上がっています。
16 Proも4K/120fps(外部ProRes対応)やApple Log/ACESに対応していましたが、ProRes RAW収録とGenlock対応は17 Proからの追加です。
フロントは、16 Proの12MP TrueDepthから、17 Proで18MPフロントカメラ(センターフレーム対応)へ。
被写体人数に応じた画角自動拡張や、縦持ちのまま横長セルフィーが撮れるなど、静止画・動画ともにフレーミング自由度が増しています(デュアルキャプチャや超強力な手ブレ補正も前面で利用)。
| 項目 | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| ■ 基本構成 | ||
| 背面カメラ構成 | 48MP × 3(超広角/広角/望遠) | 48MP(超広角)+48MP(広角)+12MP(望遠) |
| リアの倍率と焦点距離(主) | 0.5×=13mm(超広角)/ 1×=24mm(広角)/ 2×=48mm(広角センサー中央クロップ・12MP)/ 4×=100mm(望遠・光学)/ 8×=200mm(望遠・光学品質・12MP) | 0.5×=13mm(超広角)/ 1×=24mm(広角)/ 2×=48mm(広角センサー中央クロップ・12MP)/ 5×=120mm(望遠・光学・12MP) |
| ■ ズーム/焦点距離 | ||
| ズーム仕様(写真) | 8倍の光学ズームイン(100mm光学+200mmは光学品質)/2倍の光学ズームアウト/光学ズームレンジ16倍|(写真)デジタル最大40倍 | 5倍の光学ズームイン(120mm光学)/2倍の光学ズームアウト/光学ズームレンジ10倍|(写真)デジタル最大25倍 |
| 焦点距離UI(主) | 13/24/28/35/48/100/200mm(+マクロ) | 13/24/28/35/48/120mm(+マクロ) |
| ■ 静止画(出力とクロップ) | ||
| デフォルト出力 | 24MP(超高解像48MP対応) | 24MP(超高解像48MP対応) |
| クロップ時の出力 | 2×=12MP(広角中央クロップ)/8×=12MP(望遠中央クロップ・光学品質) | 2×=12MP(広角中央クロップ)/5×=12MP(望遠・光学) |
| ■ 動画 | ||
| 動画機能(主) | 4Kドルビービジョン(最大120fps)/ProRes RAW(外部記録)/Apple Log 2/ACES/Genlock | 4Kドルビービジョン(最大120fps)/ProRes(外部記録で最大4K120)/Apple Log/ACES |
| 動画デジタルズーム | 最大15× | 最大15× |
| ■ フロント/安定化 | ||
| フロントカメラ | 18MP センターフレーム対応(自動フレーミング・横長セルフィー等) | 12MP TrueDepth |
| 手ぶれ補正 | 望遠:3DセンサーシフトOIS+AF/全域で進化 | 望遠:3DセンサーシフトOIS+AF |
※「光学品質」はレンズ可動による光学ズームではなく、高解像センサーの中央クロップで解像感を維持する方式です。
※ 200mm(8×)は12MP出力の“光学品質”モード、100mm(4×)は純粋な光学。2×(48mm)も12MP出力の中央クロップです。
写真:何が新しく、どこまで撮れるようになった?
ポイントは3つ。
- 背面すべて48MP化&デフォルト24MPで“使える解像”が底上げ
- 100mm(光学)+200mm(光学品質)の二段望遠で“届く被写体”が拡大
- Photonic Engine/Smart HDR 5の改良で色・階調の安定感が向上
① 解像度と出力:24MPを基準に、48MPで後から詰められる
通常は24MP出力。
細部重視のときは48MPで撮って後からトリミングしやすくなりました。
なお2×(48mm)はメイン48MPの中央クロップで12MP出力です。
② 二段望遠:100mm(光学)と200mm(光学品質)
100mm(4×)は純粋な光学でポートレートや展示物に強い。
200mm(8×)は望遠48MPセンサーの中央部を使う“光学品質”の12MP出力で、明るい場面の遠景・ディテール抜きに有効です。
暗所はシャッター速度が厳しくなるため、夜は100mm中心が安定。
迷ったら「人物・商品=100mm/遠景・舞台=200mm」を基本に。
③ 色とトーン:Photonic Engine/Smart HDR 5で“撮って出し”が安定
肌の質感やハイライトの粘りが改善。
明部〜暗部のトーンが整いやすく、撮って出しで色が破綻しにくいのが17 Proの写真傾向です。
シーン別:どのレンズをどう使う?
- 人物・商品:100mm(4×)。背景圧縮で主役が立つ。手ブレ対策に構えを安定させる。
- 遠景・ステージ:200mm(8×・光学品質)。明るい場面で解像重視。
- 夜景スナップ:48mm or 100mmが歩留まり◎。ISOを上げすぎずシャッター速度を確保。
- 日常スナップ:24mm/28mm/35mm。被写体に寄って立体感を出す。
※ 2×(48mm)と8×(200mm)はいずれも12MP出力。2×はメイン、8×は望遠の中央クロップで解像感を確保します。
“8×光学品質”の正しい理解:物理光学ズームではなく、高解像クロップで画質確保

Appleの表記は 「最大8倍の光学ズーム」。
ここでいう“光学品質(optical-quality)”は、レンズが機械的に8倍まで動くという意味ではありません。
公式仕様が示すとおり、200mm時は12MP出力で、高解像の望遠センサーの中央部を使って解像感を担保するアプローチです(いわば“仮想の200mmレンズ”)。
同様に、2×(48mm)も12MP出力で、メインカメラの高解像センサーを中央クロップして画質を確保します。
一方で 100mm(4×)はテトラプリズムによる純粋な光学ズーム。
実運用では、日中や十分な照度がある場面は200mm(8×)も積極的に、夕景〜夜間は100mm(4×)中心が歩留まり良好。
なお、デジタルは最大40×ですが、画質重視なら“光学4×/光学品質8×”の二枚看板を基本にするのがおすすめです。
フロント18MP×センターフレーム:グループセルフィーと縦動画の快適さ
フロントの18MP センターフレームは、被写体数に応じた自動ワイド化とフレーミングで、縦持ちのまま水平・垂直の画作りを柔軟に。
また、デュアルキャプチャで前後同時のリアクション撮りや、旅行Vlogでの“語り+風景”のワンテイク収録が容易になりました。
加えて手ぶれ超補正ビデオ(Actionモード)の効果で、歩き撮りの揺れも最小限に抑えられます。
なおフロントでもProRes RAW/Apple Log 2/ACESに対応し、Vlogでも統一したカラー運用が可能です。
動画:ProRes RAW/Apple Log 2/ACES/4K120 Dolby Vision、そしてGenlock

ProRes RAW(外部記録)とApple Log 2/ACESで“後処理耐性”、4K120 Dolby Vision(Fusionメイン)で“表現幅”、Genlockで“現場連携”が強化されました。
デュアルキャプチャは4K30まで対応し、Vlogのワンテイクにも向きます。
さらにGenlock対応により、マルチカム同期待ちやLEDウォール撮影など、これまで“専用機の領域”だった現場へ踏み込みます。
周辺機材では、BlackmagicのCamera ProDockがBNC経由のGenlock/タイムコード、HDMI、複数USB-C、3.5mmオーディオなどを増設し、外部SSD記録や外部モニタを含めた実務的なリグ化を後押し。
iPhoneを“現場の1カメ”として運用する具体解が、公式アクセサリ連携で整ってきました。
実務ワークフロー:機動力と編集耐性のバランスをどう取るか
- 機動力重視:旅行やイベントのVlogなら、4K60 Dolby Visionを基本に。歩き撮りや被写体の速い動きが多い日はActionモード(2.8K60)も候補。編集はスマホ〜iPadの範囲で完結できます。
- 編集耐性重視:カラーグレーディングや合成が前提なら、Apple Log 2で収録し、ACES運用に。シャープネスやNRの“のり”を抑えつつ、4K120のスローモーションを要所で差し込むと、作品の抑揚が付きます。
- 最高画質優先:ProRes RAWはダイナミックレンジと後処理耐性が抜群ですが、外部SSD必須・発熱/容量大という“重さ”があります。重要カットだけRAW、それ以外はProRes/HEVCに落とす“ハイブリッド運用”が現実的です。
弱点と注意点:200mmの暗所・熱設計・容量
- 200mm相当は明るい場面向け:インセンサークロップで解像は保ちやすい一方、暗所ではノイズ・被写体ブレのリスクが増します。ISO上限を抑え、連写で当てるのが現実策。
- ProRes RAW/4K120は“熱と容量”が現実問題:外部SSDと給電(リグ運用)を前提に。長回しはHEVCやProRes 4:2:2へ段階的に切り替える。
- 手持ち時は“支点の作り方”が命:100mm以上は小刻みブレが乗りやすい。ストラップテンションや一脚代わりの自撮り棒で支点を増やすだけでも歩留まりが上がります。
- ストレージ運用のコツ:重要カットのみProRes RAW、それ以外はApple Log 2+ProRes/HEVCの“混在運用”にすると、画質と容量のバランスが取りやすくなります。外部SSDはUSB 3系の十分な書き込み速度を満たすモデルを選び、発熱対策に短尺で区切るのが現実的です。
17 Proの“画づくり”の傾向:iPhoneらしさのまま“引き延ばせる”
総じて17 Proの絵は、コントラストや白の抜けがスッと立つ“iPhoneらしい絵作り”を保ちながら、長めの焦点域でも解像とトーンを引き延ばせるのがポイント。
これまで“寄れないから諦める”だった被写体に、100mmと200mmの二階建てで手が届く。
動画はLog 2/ACES/ProRes RAWを軸に、「スマホで撮る→PCで仕上げる」ワークフローに本気で耐えるようになりました。
機動力と制作耐性の両輪が、いよいよスマホで噛み合ってきた印象です。
まとめ:今年“買い替える理由”は、ズームの「使える」進化と動画の「繋がる」進化

- 写真は、100mm光学+200mm光学品質で“届く画”が広がり、背面オール48MPで“使える解像”を底上げ。
- 動画は、ProRes RAW/Log 2/ACES/Genlockでプロ環境との互換性と将来性が大幅向上。4K120 Dolby Visionもインパクト大。
- フロントは18MP センターフレームで、グループセルフィー&Vlogの扱いやすさが段違い。
「被写体に寄れる、編集で詰められる、現場で繋げられる」。
17 Proのカメラは、この三拍子をスマホサイズに収めたのが価値です。
写真派は100mmの常用化、動画派はApple Log 2ベースの標準化が、今年のアップデートの恩恵を最も実感できるポイントになるはずです。